特集
荒木組のメンター制度(第3回)
前回はメンター制度の立ち上げ当時のお話を伺いました。今回は現在の様子と今後の展望を伺います。
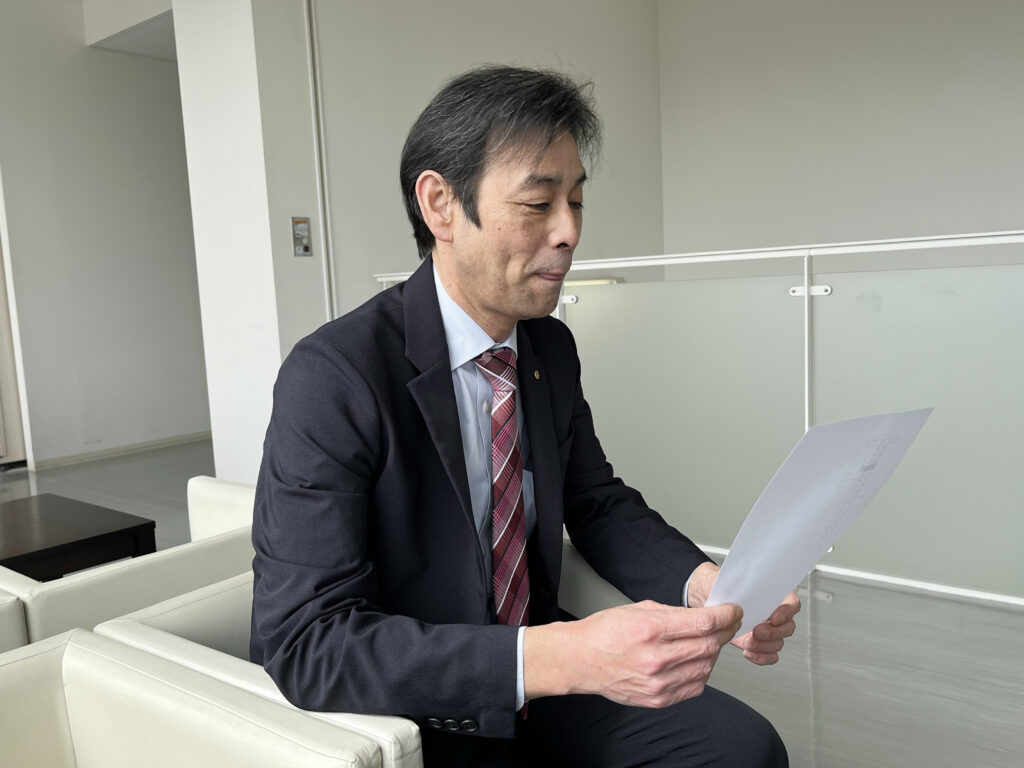
立ち上げ当初の資料をもとに、インタビューに応じていただきました
第3回―メンター制度の今とこれから
編集部(以下、編):若手社員の皆さんから、メンター制度が好評のようですね。皆さんが前向きに取り組まれているということでしょうか?
本郷部長(以下、部長):荒木組では「資格等級制度」という独自の制度があります。それは、一つひとつのステップをクリアしていくことで、次の等級に上がっていくのですが、メンターの役割を担うことが、等級を上げるための1つの条件になっています。これは、メンター制度に共通認識を持ってもらうための施策ですね。
それよりも、メンティだった社員が1年間制度を利用した後に、前向きにメンターを引き受けるようになったことが大きいです。実際に「自分は先輩にこういった話をしてもらった。だから、今度は自分が新入社員にしてあげたい」という声を聞きます。これはありがたいことです。
編:今はこの制度が軌道に乗っているという実感があるのではないですか?
部長:そうですね。この制度は同じ部署の社員をメンター・メンティとして組み合わせないというルールがあるので、メンターに立候補してくれても人数の兼ね合いで採用できないことも出てきました。少し歯痒いですね。
編:1年間メンターを担当された社員さんからは、どのような声が上がっていますか?
部長:1年間メンターとして新入社員に関わることで、会社の期待や目標、自身の成長やメンティの成長も感じられて、達成感があるようです。今のメンターは、元々メンティだったので、「(会社・先輩に)恩返しができた」という気持ちが出てくるようです。
編:すごく良い循環になっていますね!
部長:そこは本当に良くなっているなと思っています。あとは我々が、このメンター制度の大事な要素である、メンター・メンティの組み合わせを丁寧につくっていくことですね。大切なのは、今の若手社員の普段の様子を知ること。それと今の採用担当と相談しながら、誰と誰がペアになるか考えていきます。若手社員たちの人柄を知る、採用担当ならではの技術ですね。
編:メンター制度が始まってから、離職率が低下したといったような効果もあったのですか?
部長:元々、当社は離職率が低いので、その点に関しては重要なポイントではないのです。相談できる環境をつくって、職場での精神面の充実や満足度の向上を図る。1年間のメンター制度の任期が終了しても、そのペアの良い関係性が続いていくことが理想です。

研修では新しいメンターに向けて、先輩メンターから経験談を話します
これからの時代は、「個々を大事にしましょう」と教えられた世代が増えてくるでしょう。受けてきた教育の環境や価値観が大きく変わり、「多様性」が当たり前になると思います。その「多様性」によって力を発揮できるように会社を動かしていくということが、今後のミッションだと考えています。このメンター制度をベースに、会社自体が、個々の力を発揮しやすい環境になっていければよいなと思っています。
編:これからもメンター制度を充実させていきたいですね。
部長:そうですね。2025年度で8年目になり、その間、メンターの役割を担った42名の先輩社員が荒木組で活躍してくれています。今年度は11名の新入社員に対してメンター制度を運営していきます。ぜひ、アラキズムでメンターのことを追いかけてみてください(笑)。
編:分かりました!メンターさんの声なども記事にしていければと思います。本日はありがとうございました。
部長:ありがとうございました。

